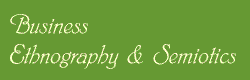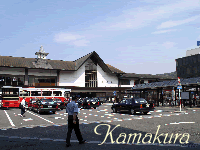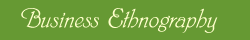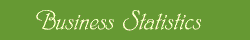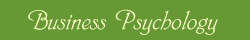実験計画法
ロサムステッド農業実験局に勤務していたR.A.フィッシャーによって1920年代に基礎付けられた統計的手法。"Design Of Experiments" を略してDOEと呼ばれる。
という2つが前提となる。
例えば、テレビ広告(因子)の効果への実験計画法の適用は、テレビ広告(因子)を行うとともにテレビ広告(因子)を行わないか、テレビ広告以外の新聞広告(因子)、街頭広告(因子)などの代替手段をを別々に行うという形をとる。
実験計画法の有名な適用例は米国の経済学者マクファデンによるサンフランシスコの地下鉄BARTの設置計画における通勤者のシェアの推計を挙げることが出来る。この実験計画では通勤者シェア6.4%に対して実際は6.2%とという結果を残した。
企業でも応用も少なくなく、チェース・マンハッタン銀行、AOLなどでの活用が知られている。
- 地域、媒体、人などの複数単位で実験を反復することで誤差分散が推定できること。
- 実験の結果に確率論を適用出来ること。つまり、実験の単位を無作為に選択することが可能なこと。
という2つが前提となる。
例えば、テレビ広告(因子)の効果への実験計画法の適用は、テレビ広告(因子)を行うとともにテレビ広告(因子)を行わないか、テレビ広告以外の新聞広告(因子)、街頭広告(因子)などの代替手段をを別々に行うという形をとる。
実験計画法の有名な適用例は米国の経済学者マクファデンによるサンフランシスコの地下鉄BARTの設置計画における通勤者のシェアの推計を挙げることが出来る。この実験計画では通勤者シェア6.4%に対して実際は6.2%とという結果を残した。
企業でも応用も少なくなく、チェース・マンハッタン銀行、AOLなどでの活用が知られている。
実験計画法の3大原則
(1)局所管理の原則
注目している要因以外の因子で結果に影響を及ぼすと考えられるものは全て一定にコントロールすべし。
(2)ランダム化の原則
実験で制御出来ない因子がある場合は注目している因子の効果と混合してしまわないようにすべし。
(3)繰り返しの原則
実験で制御できない因子の影響を除去するために同じ条件の下での繰り返しを必ず行うべし。
注目している要因以外の因子で結果に影響を及ぼすと考えられるものは全て一定にコントロールすべし。
(2)ランダム化の原則
実験で制御出来ない因子がある場合は注目している因子の効果と混合してしまわないようにすべし。
(3)繰り返しの原則
実験で制御できない因子の影響を除去するために同じ条件の下での繰り返しを必ず行うべし。
バス・モデル
t時点において既に製品を購入した消費者が全消費人口に占める割合をR(t)とする。
従って、その時点で全消費人口のうち当該製品を購入していない割合は(1-R(t))となる。このうち、新しく製品を購入しようとするイノベーターの割合をpとし、全体の普及率を見てやおら購入に踏み切る層の割合をqとする。
さて、潜在的市場規模をMとすると、t時点の現実の市場規模は、
m(t) = [p+qR(t)]*[ 1 - R(t)]*M
と表現出来る。
このモデルをFrank Bassのモデル、BASSモデルという。
[参考]Bass, Frank M., "A New Product Growth Model for Consumer Durables," Management Science, 15, (5) (January 1969), 215-227.
従って、その時点で全消費人口のうち当該製品を購入していない割合は(1-R(t))となる。このうち、新しく製品を購入しようとするイノベーターの割合をpとし、全体の普及率を見てやおら購入に踏み切る層の割合をqとする。
さて、潜在的市場規模をMとすると、t時点の現実の市場規模は、
m(t) = [p+qR(t)]*[ 1 - R(t)]*M
と表現出来る。
このモデルをFrank Bassのモデル、BASSモデルという。
[参考]Bass, Frank M., "A New Product Growth Model for Consumer Durables," Management Science, 15, (5) (January 1969), 215-227.
ロジットモデルの推定
統計解析パッケージRでロジットモデルを推定するためには、CRAN(The Comprehensive R Archive Network)からBundle of MASS,class, nnet, spatialをダウンロード。
Windowsの場合VR_7.2-2.zipファイルを解凍すると、
というフォルダとファイルが作成される。
rw****のフォルダの中の library のフォルダに一括して上書きコピー。
Rを起動して
> library(nnet);
> library(MASS);
とライブラリを読み込んだ上で、
>multinom(formula, data, weights, subset, na.action,
contrasts = NULL, Hess = FALSE, summ = 0, censored = FALSE,
model = FALSE, ...)
とすることで推定が出来る。
附属している例では
multinom(formula = low ~ ., data = bwt)
が実行される。
このパッケージに含まれている例では、出生時体重が2.5kg以上か以下かを示す low を母親の年齢(age)、母親の体重(lwt)、母親の人種(race)、母親が妊娠中に喫煙していたかどうか(smoke)、未熟児を産んだことがあるかどうか(ptd)、高血圧かどうか(ht)、被刺激性の不正子宮出血の病歴があるか(ui)、最初の3ヵ月に医者にかかった回数(ftv)によって説明するモデルとなっている。
以下が「例」のアウトプット。
> example(birthwt);
brthwt> attach(birthwt)
brthwt> race <- factor(race, labels = c("white", "black",
"other"))
brthwt> ptd <- factor(ptl > 0)
brthwt> ftv <- factor(ftv)
brthwt> levels(ftv)[-(1:2)] <- "2+"
brthwt> bwt <- data.frame(low = factor(low), age, lwt, race,
smoke = (smoke > 0), ptd, ht = (ht > 0), ui = (ui > 0), ftv)
brthwt> detach("birthwt")
brthwt> options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly"))
brthwt> glm(low ~ ., binomial, bwt)
Call: glm(formula = low ~ ., family = binomial, data = bwt)
Coefficients:
(Intercept) age lwt raceblack raceother smokeTRUE
0.82302 -0.03723 -0.01565 1.19241 0.74068 0.75553
ptdTRUE htTRUE uiTRUE ftv1 ftv2+
1.34376 1.91317 0.68020 -0.43638 0.17901
Degrees of Freedom: 188 Total (i.e. Null); 178 Residual
Null Deviance: 234.7
Residual Deviance: 195.5 AIC: 217.5
Windowsの場合VR_7.2-2.zipファイルを解凍すると、
- class_フォルダ
- mass_フォルダ
- nnet_フォルダ
- spatial_フォルダ
- description
というフォルダとファイルが作成される。
rw****のフォルダの中の library のフォルダに一括して上書きコピー。
Rを起動して
> library(nnet);
> library(MASS);
とライブラリを読み込んだ上で、
>multinom(formula, data, weights, subset, na.action,
contrasts = NULL, Hess = FALSE, summ = 0, censored = FALSE,
model = FALSE, ...)
とすることで推定が出来る。
附属している例では
multinom(formula = low ~ ., data = bwt)
が実行される。
このパッケージに含まれている例では、出生時体重が2.5kg以上か以下かを示す low を母親の年齢(age)、母親の体重(lwt)、母親の人種(race)、母親が妊娠中に喫煙していたかどうか(smoke)、未熟児を産んだことがあるかどうか(ptd)、高血圧かどうか(ht)、被刺激性の不正子宮出血の病歴があるか(ui)、最初の3ヵ月に医者にかかった回数(ftv)によって説明するモデルとなっている。
以下が「例」のアウトプット。
> example(birthwt);
brthwt> attach(birthwt)
brthwt> race <- factor(race, labels = c("white", "black",
"other"))
brthwt> ptd <- factor(ptl > 0)
brthwt> ftv <- factor(ftv)
brthwt> levels(ftv)[-(1:2)] <- "2+"
brthwt> bwt <- data.frame(low = factor(low), age, lwt, race,
smoke = (smoke > 0), ptd, ht = (ht > 0), ui = (ui > 0), ftv)
brthwt> detach("birthwt")
brthwt> options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly"))
brthwt> glm(low ~ ., binomial, bwt)
Call: glm(formula = low ~ ., family = binomial, data = bwt)
Coefficients:
(Intercept) age lwt raceblack raceother smokeTRUE
0.82302 -0.03723 -0.01565 1.19241 0.74068 0.75553
ptdTRUE htTRUE uiTRUE ftv1 ftv2+
1.34376 1.91317 0.68020 -0.43638 0.17901
Degrees of Freedom: 188 Total (i.e. Null); 178 Residual
Null Deviance: 234.7
Residual Deviance: 195.5 AIC: 217.5
ロジットモデル
ある商品を購入した人の割合をP、購入しなかった人の割合を1−Pとするとき
log(P/(1-P))
をロジットと呼ぶ。
その商品の効用をVとした時に、
log(P/(1-P)) = α + βlogV
のように線形の関係がある場合にそのモデルをロジットモデルと言う。
このロジットモデルは次のようにも変形できる。
P=1 / [1+exp( -α - βlogV)]
プロビットモデルと同様にロジットモデルもS字曲線を描き、効用Vが0に近づくと購入割合Pは0に近づく。
購入者にとって何らの効用をもたらさない商品を購入する人の割合は0であると通常考えられるため至極当然と言える。
log(P/(1-P))
をロジットと呼ぶ。
その商品の効用をVとした時に、
log(P/(1-P)) = α + βlogV
のように線形の関係がある場合にそのモデルをロジットモデルと言う。
このロジットモデルは次のようにも変形できる。
P=1 / [1+exp( -α - βlogV)]
プロビットモデルと同様にロジットモデルもS字曲線を描き、効用Vが0に近づくと購入割合Pは0に近づく。
購入者にとって何らの効用をもたらさない商品を購入する人の割合は0であると通常考えられるため至極当然と言える。
世帯主法
家族類型別世帯数の推計を行う際に用いられる手法。
世帯数が世帯主数にほぼ等しいことを利用し
世帯数=人口×人口に占める世帯主数の割合(世帯主率)
として計算される。
世帯主率は、男女別、年齢別で相違するために、通常は男女別、年齢5歳階級の15歳以上15区分の統計が用いられる。
ここで、
家族類型別世帯主率=家族類型別世帯数÷配偶関係別人口
として求める。
世帯数が世帯主数にほぼ等しいことを利用し
世帯数=人口×人口に占める世帯主数の割合(世帯主率)
として計算される。
世帯主率は、男女別、年齢別で相違するために、通常は男女別、年齢5歳階級の15歳以上15区分の統計が用いられる。
ここで、
家族類型別世帯主率=家族類型別世帯数÷配偶関係別人口
として求める。
イノベーションの普及
E.M.ロジャースの「イノベーション普及学」によると、製品の顧客層は
に分類される。
革新的な製品が出るとまず、イノベータと呼ばれる人々が採用する。しかし、この層の人々の消費行動が社会全体への製品の普及に直接的に影響を及ぼすということはない。
次に、オピニオンリーダーと呼ばれる層に分類される社会に大きな影響力を持ち、富裕層でもある人々がイノベーションの体化した製品を購入する。
この段階が将に普及曲線のテイクオフ(離陸)となる。
次に、主観的には製品選択の判断をすることはないものの、世間一般の流行からは乗り遅れまいとする人々の層がオピニオンリーダーの消費行動を模倣する。この層はアーリーマジョリティと呼ばれる。従来は大半の日本人はこの層に分類されると見なされてきた。
アーリーマジョリティは主観的に判断を行わないとしても当該製品が普及していく上で決定的な地位を占める。
そして、最後に残るのは、半ば強制的な社会的条件が整わない限りは当該製品を購入しようとはしない人々、伝統主義者となる。
こうした分類に加えて、E.M.ロジャーズは、次のような相互の社会経済的特性を挙げている。
- イノベーター(革新的採用者)...2.5%...-2sd
- オピニオンリーダー(初期少数採用者)...13.5%...-sd
- アーリーマジョリティ(初期多数採用者)...34.0%
- レイトマジョリティ(後期多数採用者)...34.0%...+sd
- ラガーズ(伝統主義者)...16.0%
に分類される。
革新的な製品が出るとまず、イノベータと呼ばれる人々が採用する。しかし、この層の人々の消費行動が社会全体への製品の普及に直接的に影響を及ぼすということはない。
次に、オピニオンリーダーと呼ばれる層に分類される社会に大きな影響力を持ち、富裕層でもある人々がイノベーションの体化した製品を購入する。
この段階が将に普及曲線のテイクオフ(離陸)となる。
次に、主観的には製品選択の判断をすることはないものの、世間一般の流行からは乗り遅れまいとする人々の層がオピニオンリーダーの消費行動を模倣する。この層はアーリーマジョリティと呼ばれる。従来は大半の日本人はこの層に分類されると見なされてきた。
アーリーマジョリティは主観的に判断を行わないとしても当該製品が普及していく上で決定的な地位を占める。
そして、最後に残るのは、半ば強制的な社会的条件が整わない限りは当該製品を購入しようとはしない人々、伝統主義者となる。
こうした分類に加えて、E.M.ロジャーズは、次のような相互の社会経済的特性を挙げている。
- 早期採用者と後期採用者との間に年齢の相違はない
- 早期採用者は後期採用者と比較して高学歴
- 早期採用者は後期採用者と比較して社会的地位が高い
- 早期採用者は後期採用者と比較して上方へと社会移動をすることが多い
- 早期採用者は後期採用者と比較して自給自足よりも商業的経済を志向
プロデジー・モデル
顧客の購買行動を強制的遷移行列に落とし込んだ上で無構造市場仮説と他の市場構造仮説とを比較・検証していくというモデル。
強制的遷移行列というのは、顧客が選択しようとする製品がない場合に他のどの製品を選択するかを観測したデータからなる行列。
PRODEGY MODEL
強制的遷移行列というのは、顧客が選択しようとする製品がない場合に他のどの製品を選択するかを観測したデータからなる行列。
PRODEGY MODEL
プラグマティシズム
「あらゆる概念の要素は知覚の門を通って論理的思想に入り、目的的行動の門を通って外に出る。これらの二つの門で通過証明を示すことが出来なければ理性の認可を受けていないとして逮捕されなければならない」
パース、論文集第5巻
この立場に立つと、つまり、推論なしには目的的行動はありえないことになる。
そして、個々人の推論の立て方のメカニズムが解れば個々人の目的的行動を知ることが出来ることになる。
パース、論文集第5巻
この立場に立つと、つまり、推論なしには目的的行動はありえないことになる。
そして、個々人の推論の立て方のメカニズムが解れば個々人の目的的行動を知ることが出来ることになる。
無構造市場仮説
ある特定の製品が販売されなくなった場合に、その特定の製品のシェアに応じて他の製品のそれぞれのシェアが比例的に上昇するという考え方。
しばしばマーケティングにおける帰無仮説とされる。
しばしばマーケティングにおける帰無仮説とされる。
市場の規定
全体としての市場がどのようなサブマーケットによって構成されているかを明らかにすること。
習慣形成仮説
「過去に享受された実際の消費は、人間の整理学的・心理学的組織に印象づけられて習慣、風習、標準および水準を形成し、これは消費行動における慣性あるいは履歴効果をもたらす。・・・過去の消費が現在の消費行動におよぼす習慣持続効果は、時間tが小さいときには大きく、tが大となるにつれて次第に減少する。・・・換言すれば、習慣持続効果は連続的であり、時間の逆関数として表現できる」
Brown(1952)
Brown(1952)