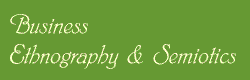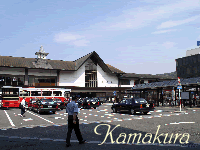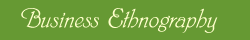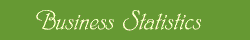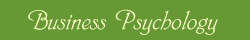誕生占星術
カルデア人が考案した占星術。現在の東西の占星術のルーツに当たる。
産まれた瞬間に水星、金星、火星、木星、土星がそれぞれどういう位置関係にあったが人の運命を決定するという思想。
genethlialogia。
産まれた瞬間に水星、金星、火星、木星、土星がそれぞれどういう位置関係にあったが人の運命を決定するという思想。
genethlialogia。
夢の源
S.フロイトによれば、夢は外的あるいは客観的感覚興奮、内的であるけれども主観的な感覚興奮、内的であり器質的な身体刺激、そして、純粋に心に源を持つものに完全に分類される。
ユングの無意識
C.G.ユングは人の無意識を個人的無意識と集合的無意識の二つからなると考えた。
個人的無意識は過去の記憶や経験などが自我の統合を保つために意識から無意識に潜ったもののこと。
一方、集合的無意識というのは、個人的な経験を超えて、集団に属する全ての人に共通する無意識のことであり、文化的無意識ともいう。
個人的無意識は過去の記憶や経験などが自我の統合を保つために意識から無意識に潜ったもののこと。
一方、集合的無意識というのは、個人的な経験を超えて、集団に属する全ての人に共通する無意識のことであり、文化的無意識ともいう。
エス
意識の奥底にあって人の行動の真の動機となっている無意識の中にある性的衝動(リピドー)や攻撃本能などの心的エネルギーのこと。
心的エネルギーのままに行動すれば無秩序に結び付くが、それをコントロールするのが自我。
心的エネルギーのままに行動すれば無秩序に結び付くが、それをコントロールするのが自我。
心
精神分析学の創始者S.フロイトは人の心は「意識」、「前意識」、「無意識」という三層構造を持つと考えた。
意識というのは自分の思考や行動を自分自身で分かっている状態。
前意識というのは普通は意識に上ってくることはないけれども注意や意思によって思い出せる領域のこと。
そして、無意識というのは注意や意思によっても意識することが難しいけれども、自分の行動の源となっている領域のことを指す。
意識というのは自分の思考や行動を自分自身で分かっている状態。
前意識というのは普通は意識に上ってくることはないけれども注意や意思によって思い出せる領域のこと。
そして、無意識というのは注意や意思によっても意識することが難しいけれども、自分の行動の源となっている領域のことを指す。
葛藤
K.レヴィンは同じ程度の同時に存在する欲求の選択に悩む葛藤は三つに分けている。
第1は、どちらもしたいけれども両方を選択する事は出来ないため迷うという「接近=接近型」。
第2は、どちらもやりたくない、どちらも避けたいのだけれども、どちらかを受け入れなければならないという「回避=回避型」。
第3は、欲望はあるのだけれども、それを満たすためには代償を伴うというケースの「接近=回避型」。
「回避=回避型」の場合には選択はしてもストレスが溜まる。「接近=接近型」では選択への後悔に悩む。
第1は、どちらもしたいけれども両方を選択する事は出来ないため迷うという「接近=接近型」。
第2は、どちらもやりたくない、どちらも避けたいのだけれども、どちらかを受け入れなければならないという「回避=回避型」。
第3は、欲望はあるのだけれども、それを満たすためには代償を伴うというケースの「接近=回避型」。
「回避=回避型」の場合には選択はしてもストレスが溜まる。「接近=接近型」では選択への後悔に悩む。
2種類の夢
アルテミドロスは夢を二種類に分けることが出来ると考えたとされる。
第1は、現在あるいは過去だけにのみ影響を受けているもの。
第2は、預言、夢判断、夢占いと縁が深いもの。
第2のものは客観的ではないことから科学の分析の範疇には含まれ難い。しかし、人々にとっては何世紀にもわたって大きな関心事であったことは紛れもない事実でもある。
第1は、現在あるいは過去だけにのみ影響を受けているもの。
第2は、預言、夢判断、夢占いと縁が深いもの。
第2のものは客観的ではないことから科学の分析の範疇には含まれ難い。しかし、人々にとっては何世紀にもわたって大きな関心事であったことは紛れもない事実でもある。
六国史
日本で平安時代に編纂された「日本書紀」、「続日本紀」、「日本後記」、「続日本後記」、「文徳実録」、「三代実録」の6つの国史のこと。
「日本書紀」の編纂中の692年に叙述の必要性から日本で初めての公式のカレンダー(暦)である元嘉暦・儀鳳暦併用暦が施行された。
「日本書紀」の編纂中の692年に叙述の必要性から日本で初めての公式のカレンダー(暦)である元嘉暦・儀鳳暦併用暦が施行された。
宿曜道
中国の西晋から東晋時代にかけて密教と陰陽道とが融合して生み出された思想。
「舎頭諌太子二十八宿経」などを基本経典とした。
日本でも平安時代に密教が広まると宿曜道(すくようどう)も知られるようになっていった。
「舎頭諌太子二十八宿経」などを基本経典とした。
日本でも平安時代に密教が広まると宿曜道(すくようどう)も知られるようになっていった。
法相宗
南都六宗の一つ。
唐の玄奘を始祖とし、弟子の窺基が宗派を形成。日本へは元興寺の道昭が伝えた。
大乗・唯識派の流れを汲み「成唯識論」を教義の中心に据える。
薬師寺、興福寺が本山。
唐の玄奘を始祖とし、弟子の窺基が宗派を形成。日本へは元興寺の道昭が伝えた。
大乗・唯識派の流れを汲み「成唯識論」を教義の中心に据える。
薬師寺、興福寺が本山。