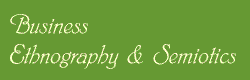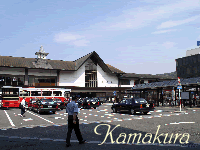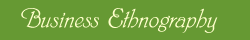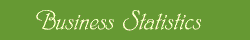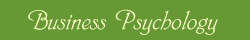トーマス・ベイズ Thomas Bayes( 1702 - 1761 )
長老教会派牧師にしてアマチュアの数学者。
不特定の条件下における特定の事象の発生確率を予測する統計理論を構築した。これがベイズ理論。
その理論は、彼の死後、1763年に「偶然の理論における1問題を解くための試み(Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances)」という論文で世に出た。
この論文の中の一文、「未来を推測するには過去を振り返らなければならない(To see the future, one must look at the past.)」は有名。
ベイズの定理は、事前確率 P(X)、事後確率 P(X|E)、尤度 P(E|X)として
P(X|E) = P(E|X)P(X) / P(E)
P(E) = Σ P(E|X)P(X)
と表現される。
同じ定式化はピエール・シモン・ラプラス(1749-1827)によってもなされている。しかし、フィッシャー(1857-1936)とK・ピアソン(1857-1936)らによって一旦はベイズ統計は非主流とされた。
このように確率が逐次的に修正されていくという考え方は客観的科学とは相容れないと考えられたのか、あるいは、その理論の提唱者がアマチュアであり、しかも、生前には、神の存在を方程式で説明できると主張していたような人物であったためだろうか。
ともかくも、一時期はトンデモ科学と見なされてきたベイズ統計は、第二次大戦後にD・V・リンドレイや A・ワルド、L・J・サベージらによって、科学として息を吹き返した。

不特定の条件下における特定の事象の発生確率を予測する統計理論を構築した。これがベイズ理論。
その理論は、彼の死後、1763年に「偶然の理論における1問題を解くための試み(Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances)」という論文で世に出た。
この論文の中の一文、「未来を推測するには過去を振り返らなければならない(To see the future, one must look at the past.)」は有名。
ベイズの定理は、事前確率 P(X)、事後確率 P(X|E)、尤度 P(E|X)として
P(X|E) = P(E|X)P(X) / P(E)
P(E) = Σ P(E|X)P(X)
と表現される。
同じ定式化はピエール・シモン・ラプラス(1749-1827)によってもなされている。しかし、フィッシャー(1857-1936)とK・ピアソン(1857-1936)らによって一旦はベイズ統計は非主流とされた。
このように確率が逐次的に修正されていくという考え方は客観的科学とは相容れないと考えられたのか、あるいは、その理論の提唱者がアマチュアであり、しかも、生前には、神の存在を方程式で説明できると主張していたような人物であったためだろうか。
ともかくも、一時期はトンデモ科学と見なされてきたベイズ統計は、第二次大戦後にD・V・リンドレイや A・ワルド、L・J・サベージらによって、科学として息を吹き返した。