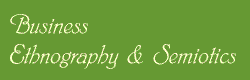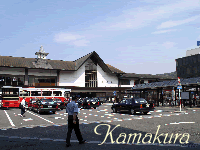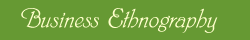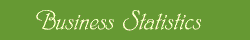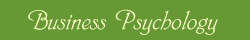リレーションシップ再考
情報科学技術(IT)の進化はマーケティングの分野にも大きな変革をもたらした。
こうした変化はコトラーが目指した『放っておけば浅薄な余興でしかなかったものに、科学とシステムを導入』するというモダン・マーケティングを更に一層加速するものだったとも言える。ワン・トゥ・ワン・マーケティング、CRMといった科学的装いを纏ったツールを見れば頷けるだろう。
しかし、
『「我々はリレーションシップ・マーケティングに力を入れている」と自負する企業は、いまだかつてないほど必至に顧客情報を収集して、あらゆる顧客のニーズや嗜好に合わせよう、考えられる限りのサービスを提供しようと懸命である。しかし、このやり方では顧客を喜ばせる結果とはならない』
David Glen Mick,Susan Fournier,Susan Dobscha,"Preventing the Premature Death of Relationship Marketing",HBR 1998.1-2
と指摘されてもいる。
曰く、顧客と企業とのリレーションシップはギブ・アンド・テイクの関係が成立して初めて成り立つ。果たして、企業のマーケティング担当者はより多くのデータを効率的に収集することで顧客を、そして顧客の情報を囲い込むということだけに集中し、自分が収集しようとするものに等しいかそれ以上のものを顧客に対して与えることが少ない。
これでは、ギブ・アンド・テイクではない。
上記論文では次のようにも付け加える。
リサーチャーは顧客の理解を第1の仕事とする消費者専門家に留まるべきではなく、『ターゲット顧客の実像を全社に伝え、理解させ、各業務を展開する責任を負った戦略家』たるべしと。
社内のリサーチャーがこのような本来の役割を果たしてこそ、本当の意味でのリレーション・マーケティングが実現する。情報技術はこうした上でのツールの一つでしかないということは肝に銘じておくべきだろう。そして、ギブ・アンド・テイクの関係を築く鍵はココにあるように感じる。
また、『八○年代、広告代理店の法人顧客担当者や定性調査の専門家が』データを収集し分析し新製品のコンセプトを洗い出していたが、こうした業務こそは企業の競争力のコアであり企業の内部で取り組むべきであるとする。
このように、マーケティングは企業のコア中のコアであるということを理解して実践している日本企業は意外に少ない。繰り返すが情報技術の進歩によって高度なマーケティングを手間を掛けずに行えるようになってきている。しかし、リレーションシップを築くということは単に技術の適用だけでは無理であり、更には手を抜くということも有り得ないということを再認識させてくれる論文であると言える。
こうした変化はコトラーが目指した『放っておけば浅薄な余興でしかなかったものに、科学とシステムを導入』するというモダン・マーケティングを更に一層加速するものだったとも言える。ワン・トゥ・ワン・マーケティング、CRMといった科学的装いを纏ったツールを見れば頷けるだろう。
しかし、
『「我々はリレーションシップ・マーケティングに力を入れている」と自負する企業は、いまだかつてないほど必至に顧客情報を収集して、あらゆる顧客のニーズや嗜好に合わせよう、考えられる限りのサービスを提供しようと懸命である。しかし、このやり方では顧客を喜ばせる結果とはならない』
David Glen Mick,Susan Fournier,Susan Dobscha,"Preventing the Premature Death of Relationship Marketing",HBR 1998.1-2
と指摘されてもいる。
曰く、顧客と企業とのリレーションシップはギブ・アンド・テイクの関係が成立して初めて成り立つ。果たして、企業のマーケティング担当者はより多くのデータを効率的に収集することで顧客を、そして顧客の情報を囲い込むということだけに集中し、自分が収集しようとするものに等しいかそれ以上のものを顧客に対して与えることが少ない。
これでは、ギブ・アンド・テイクではない。
上記論文では次のようにも付け加える。
リサーチャーは顧客の理解を第1の仕事とする消費者専門家に留まるべきではなく、『ターゲット顧客の実像を全社に伝え、理解させ、各業務を展開する責任を負った戦略家』たるべしと。
社内のリサーチャーがこのような本来の役割を果たしてこそ、本当の意味でのリレーション・マーケティングが実現する。情報技術はこうした上でのツールの一つでしかないということは肝に銘じておくべきだろう。そして、ギブ・アンド・テイクの関係を築く鍵はココにあるように感じる。
また、『八○年代、広告代理店の法人顧客担当者や定性調査の専門家が』データを収集し分析し新製品のコンセプトを洗い出していたが、こうした業務こそは企業の競争力のコアであり企業の内部で取り組むべきであるとする。
このように、マーケティングは企業のコア中のコアであるということを理解して実践している日本企業は意外に少ない。繰り返すが情報技術の進歩によって高度なマーケティングを手間を掛けずに行えるようになってきている。しかし、リレーションシップを築くということは単に技術の適用だけでは無理であり、更には手を抜くということも有り得ないということを再認識させてくれる論文であると言える。