


原木中山駅
駅の開業は1969[昭和44]年3月29日であり, 東西線が東陽町駅から西船橋駅まで延伸された際に新設された.これにより, 東京メトロ[当時は帝都高速度交通営団]が千葉県内に路線を延ばすこととなり, 都心と千葉県西部の住宅地を直接結ぶ通勤路線として大きな意義を持った.開業当初から周辺の宅地化が進行し, 高度経済成長期における首都圏ベッドタウンの発展を支える交通拠点として機能してきた.
駅名の原木中山は, 市川市原木と船橋市中山という二つの地名を組み合わせたものである.原木はばらきと読み, 市川市の伝統的な地名である.江戸時代には原木村として存在し, 農村地帯として発展していた.中山は船橋市の地名であり, 古くから集落が形成されてきた地域である.なお, 近隣には中山法華経寺[日蓮宗の大本山]が所在するが, その最寄り駅はJR総武線の下総中山駅であり, 原木中山駅からは離れている.駅の北側には市川市原木地区が, 南側には船橋市中山地区が隣接しており, 駅の利用圏は両市にまたがる.このため, 開業に際しては両地域の利便性を考慮し, 双方の地名を併記した駅名が採用されたのである.
原木中山駅から東へ徒歩約7-8分の場所には, 日蓮宗の寺院・原木山妙行寺が所在する.同寺は江戸時代中期の1678[延宝6]年に創建された寺院であり, 特に全国の日蓮宗寺院の僧侶が冬季に修行を行う大荒行堂が設けられていることで知られる.大荒行堂は修行僧が百日間にわたり水行・読経を続ける厳しい修行の場であり, 宗門内では特に重視される修行道場である.原木中山駅はその最寄駅にあたり, 荒行期間には全国各地から僧侶や関係者が訪れる.門扉や柱に多くの彫刻が施された山門があり, 庭園も含め綺麗に整備されている美しい寺院である.
さらに, 当駅周辺には歴史的交通網の痕跡も残る.1909年から1918年まで, この地域には東葛人車鉄道が走っていた.東葛人車鉄道は明治末期から大正初期にかけて営業した人車軌道であり, 中山村深町から鎌ケ谷村本田を経て行徳方面を結んでいた.路線は木下街道[現・千葉県道59号市川印西線]上に主に敷設され, サツマイモやムギなどの貨物輸送を中心に旅客輸送も行っていた.中山荷扱所が設けられ, 後には中山駅前[現・下総中山駅]までの延伸も行われた.現在の原木中山駅周辺も, この人車軌道の路線圏内に含まれており, 地域の交通史の一部を形成している.東葛人車鉄道は1918年に営業を廃止し, 会社も解散したが, その記憶は地域史として今に伝えられている.
@2025-10
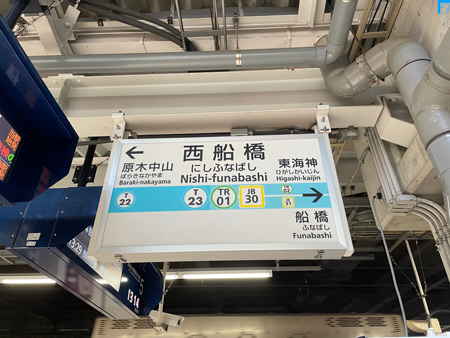



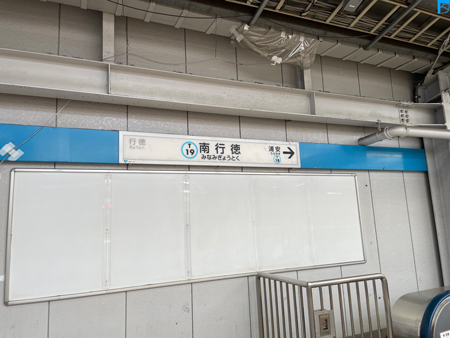



















今日も街角をぶらりと散策.
index