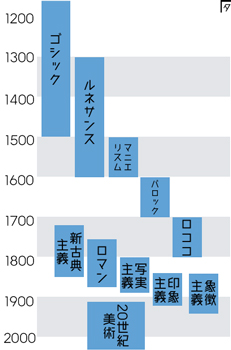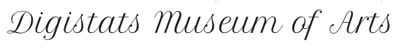


伝讃岐国出土袈裟襷文銅鐸は, 江戸時代に讃岐国[現在の香川県]で発見されたと伝えられる弥生時代後期[紀元前2-紀元1世紀頃]の青銅器である.発見の詳細な状況や正確な出土地は不明であるが, 古来より著名な銅鐸として知られてきた.現在は東京国立博物館に所蔵され, 1951年[昭和26年]6月9日に国宝に指定されている.
この銅鐸は, 吊り下げ用の鈕[ちゅう]と, そこから下方に広がる身から成る.身は扁平な円筒状で, 上から下へと次第に広がっている.装飾は浮き上がった線[突線]で構成され, 鋸歯文, 連続渦巻文, 綾杉文が施されている.また, 身の表裏は斜格子文の帯によって六区に分けられており, その区切りが僧侶の袈裟の襷掛けに似ていることから「袈裟襷文銅鐸」と呼ばれる.
製作時期は弥生時代後期の紀元前2世紀末から紀元1世紀頃と推定され, 銅鐸の発展過程における最終段階である突線鈕式銅鐸に属する.袈裟襷文銅鐸はその代表的作例であり, 特に近畿地方を中心に分布することから, しばしば近畿式銅鐸とも称される.
本銅鐸の重要性は, 優れた造形美と高度な鋳造技術にある.均整のとれた形態は, 当時の青銅器製作の到達点を示すものである.特に注目すべきは, 神戸市桜ヶ丘遺跡出土の第4号・第5号銅鐸や, 江戸時代の画家・谷文晁[たにぶんちょう]が所蔵していたと伝えられる銅鐸[現存せず, 拓本と模写のみが残る]との密接な類似性である.これらはいずれも区画の中に同様の絵画的文様を描き込んでおり, 伝讃岐国出土銅鐸と桜ヶ丘出土銅鐸とが同一の文化圏あるいは同じ集団によって製作された可能性を示している.
銅鐸は弥生文化を代表する日本固有の青銅器であり, 当初は高さ20cm前後の小型の鳴器[かね]として登場したが, 次第に大型化し, やがて実際に鳴らす機能よりも祭祀的・象徴的性格が強まった.本銅鐸はそうした発達史の最終段階を代表する作品であり, 日本古代史および弥生文化研究において極めて重要な価値を有する文化財である.
'Beauty is truth, truth beauty,'-that is all Ye know on earth, and all ye need to know.
John Keats,"Ode on a Grecian Urn"