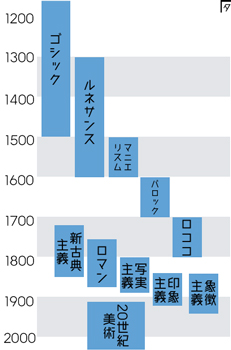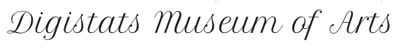


日本神話に登場する女神・木花咲耶姫命[このはなさくやひめのみこと]を主題とした堂本印象[1891〔明治24〕12-25/1975〔昭和50〕-09-05]による作品.本作は, 堂本印象が伝統的日本画の技法を継承しながらも, 近代的造形感覚を導入しようとした時期に制作されたものであり, 古典主題の再解釈という点において意義深い作品である.
木花咲耶姫は, 『古事記』および『日本書紀』において天孫降臨神話に登場する女神であり, 天照大神の孫・瓊瓊杵尊[ににぎのみこと]の妻として知られる.山の神・大山津見神[おおやまつみのかみ]の娘であり, 姉に石長比売[いわながひめ]を持つ.瓊瓊杵尊は石長比売を醜いとして父のもとに送り返し, 木花咲耶姫のみを娶ったため, 天皇の寿命が短くなったという神話が伝えられている.また, 木花咲耶姫は一夜で懐妊したことを疑われ, その身の潔白を証明するために産屋に火を放って出産したという火中出産の神話でも知られる.その名は「木の花が咲くように美しい姫」を意味し, 桜の女神, あるいは富士山の神として信仰されてきた.「桜花のように咲き誇り, やがて散る」生命のはかなさと美を象徴する存在とされてきた.日本神話における女性的自然美の象徴として, 古来より文学や美術の題材としてしばしば取り上げられてきた.堂本印象はこの神話的存在に新たな生命を与え, 象徴的な造形として表現している.
画面には, 気高くも優美な姿の女神が描かれ, 堂本印象特有の流麗な線描と色彩構成が調和している.印象はこの女性像を通じて, 自然と人間, 生成と消滅, 美と無常という日本美の根源的主題を表現しているのである.
堂本印象の本名は堂本三之助.京都市立美術工芸学校[現・京都市立銅駝美術工芸高等学校]で学んだ後, 西山翠嶂に師事し, 京都画壇の中心的存在として活躍した.明治から昭和にかけての長い画業において, 伝統的な日本画の様式を基礎としながら, 西洋絵画の影響や抽象表現を積極的に吸収し, 独自の様式を確立した.彼の画業には, 古典主題の再構築と現代的精神の融合という明確な志向があり, 木華開耶媛はその一例といえる.特にこの作品では, 日本画の伝統的技法と近代的な造形感覚が融合しており, 近代日本画の展開を示す作例となっている.
堂本印象は1944[昭和19]年に帝室技芸員に任命され, 戦後は1961[昭和36]年に文化勲章を受章するなど, 日本画壇において高い評価を受けた.また, 晩年には抽象表現へと作風を大きく転換し, 多様な芸術的探求を続けた画家としても知られている.
本作が所蔵されている京都府立堂本印象美術館は, 堂本印象自身が設計に関与し, 1966[昭和41]年に開館した美術館である.建築には印象の芸術理念が反映されており, 堂本印象の作品を中心に展示している.美術館は京都市北区にあり, 印象の画業を総合的に鑑賞できる施設として, 現在も多くの来館者を迎えている.木華開耶媛はその中でも, 印象の古典主題への探究を示す重要な作品の一つとして位置づけられている.
'Beauty is truth, truth beauty,'-that is all Ye know on earth, and all ye need to know.
John Keats,"Ode on a Grecian Urn"