 |
|
EPS(Earnings Per Share)
 「企業の経営状況を判断するためのいろいろな指標があるし、また、これがあればというか、これで全てを判断できるなんて銘打った指標の開発も行われている。でも、帯に短し襷に長しというところが本当のところ。それに、気を付けなければいけないのが、特定の業種にとっては非常に役に立つものだったりしても、違う業種との比較をする際には役に立たないという場合があるっていうこと」 「企業の経営状況を判断するためのいろいろな指標があるし、また、これがあればというか、これで全てを判断できるなんて銘打った指標の開発も行われている。でも、帯に短し襷に長しというところが本当のところ。それに、気を付けなければいけないのが、特定の業種にとっては非常に役に立つものだったりしても、違う業種との比較をする際には役に立たないという場合があるっていうこと」
 「企業ごとの特性というのもあるけど、同じ業種に属している企業の間では比較的共通の要素が大きいと言えるから、同じ業種の企業を比較する際には共通の経営指標を比較すれば良いことになるのよね。 「企業ごとの特性というのもあるけど、同じ業種に属している企業の間では比較的共通の要素が大きいと言えるから、同じ業種の企業を比較する際には共通の経営指標を比較すれば良いことになるのよね。
だけど、違う業種に属している企業を比較する場合には、企業同士の間で共通要素が少ないことが多いから簡単には比較出来ないということになる。
もっとも、適切に標準化あるいは基準化することで比較を可能にするという裏技もあるにはある」
 「そうした面倒くさいことをいちいち考えなくても複数の企業同士の比較を出来る指標の一つにEPS、一株当たり利益というものがあるね。 「そうした面倒くさいことをいちいち考えなくても複数の企業同士の比較を出来る指標の一つにEPS、一株当たり利益というものがあるね。
もうこれは、いろいろある指標の中では非常に貴重なものの一つ。
どうやって計算するかっていうと、
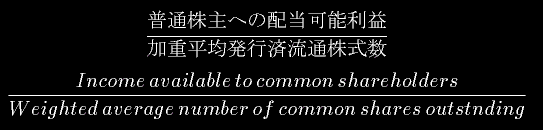 」 」
 「何だか、この定義式を見ると随分簡単なように思えるわね。まぁ、EPSの場合は企業が計算して公開していたりするから、自分でわざわざ計算するまでもないかも。 「何だか、この定義式を見ると随分簡単なように思えるわね。まぁ、EPSの場合は企業が計算して公開していたりするから、自分でわざわざ計算するまでもないかも。
それでも、基本を押さえておく必要はあるから、と。
まず、普通株主への配当可能利益というのは、当期純利益(Net Income)から優先配当(Preferred
dividends)を引いたものね]
 「そうだけど、優先配当(Preferred dividends)というのが曲者。 「そうだけど、優先配当(Preferred dividends)というのが曲者。
優先株主への配当なんだけど、累加式優先株式と非累加式優先株式があるわけだよね。
そもそも、取締役会が配当することを見送った場合には優先株主も普通株主も配当を得るということは出来ない。だけど、累加式優先株式の場合は見送られた配当金が実際に配当がある年にまで繰り越される。ということは、その分は配当を見送るかどうかに関係なく、普通株主への配当可能な利益だということにはならない」
 「だから、累加式優先株式の場合は取締役会が配当宣言したかどうかに関係なく優先配当の分を当期純利益から差し引く。 「だから、累加式優先株式の場合は取締役会が配当宣言したかどうかに関係なく優先配当の分を当期純利益から差し引く。
一方で、非累加式優先株式の場合は取締役会が配当するよって宣言した場合にだけ当期純利益から優先配当を差し引くのね」
 「ここまでが分子。 「ここまでが分子。
次ぎは分母。加重平均発行済流通株式数。これって名前が長いよ。ジュゲムジュゲムみたい。長ったらしい名前だけど、つまりは発行済流通株式を加重平均したものだってことだね。
分かりにくいなぁ。
普通株式を発行済流通だった期間に応じて加重平均するってことなわけだ」
 「注意しなければならないのは、自己株式は流通していないわけだから、発行済流通ではないので含めないってことと、株式配当(stock
dividends)と株式分割(stock splits)は、それぞれが行われた日に関係なく期首に行われたものと見做すってことね」 「注意しなければならないのは、自己株式は流通していないわけだから、発行済流通ではないので含めないってことと、株式配当(stock
dividends)と株式分割(stock splits)は、それぞれが行われた日に関係なく期首に行われたものと見做すってことね」
 「例えば、 「例えば、
| 1月1日 |
3,000株(普通株) |
| 4月1日 |
500株(普通株)発行 |
| 8月1日 |
10%の株式配当実施 |
| 12月1日 |
200株の自己株式取得 |
という場合の加重平均発行済流通株式数を計算してみようか」
 「 「
| 1月1日から3月末までの3ヵ月 |
3,000株+3,000株×10%=3,300株 |
| 4月1日から11月末までの8ヵ月 |
3,300株+500株+500株×10%=3,850株 |
| 12月1日からの1ヵ月 |
3,850 - 200 = 3,650株 |
ということになるから、
3,300×3/12+3,850×8/12+3,650×1/12=3,695.8株
ということね」
|
|