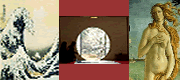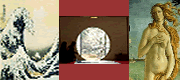|
[法の概念について]
1、「法」とは一体何であるのかについて、古来から様々な説・定義がなされてきた。
「法」の学問的定義に関しては、その論者の数ほどの定義が存在しているといってよい。このような法の学問的定義の多様性を前にして、論者の中には定義という法の概念を規定する理論的意義に対して疑問を呈するものもいる。
例えば、グランヴィル・ウィリアムズ(Granville L.Williams)は、定義というものはなんらの重要性を持たないとして、法の定義否定論を展開した。
しかし、法という概念が時代や民族、国家によって多様性を持ちながらも、その発展形態の中において、時代や民族、国家を超えた共通性・類似性を帯びていることは否定し難い。この事実を踏まえるとき、法の定義を単なる言葉の問題として、重要性を否定することはできないといえる。
2、そもそも、法は、具体的な歴史的地理的環境の中において、社会の様々な要請に応えつつ変化するという、いわば有機的実体を有しているといえる。
そうであるならば、法というものの概念について、その歴史的、民族的、国家的背景を全く捨象した形で法の普遍的定義を確立するということは非常な困難が伴うものとなる。 すなわち、法は、ある種の社会経済的・政治的勢力によって創造される。このことは、法は創造される段階において既にその時代背景を色濃く反映させた鏡となっている。
そして、法は、その実現の段階においても社会経済の要請とは無縁ではありえない。けだし、法の直接の源が慣習であるにせよ制定法であるにせよ、その要請を担保するためには、組織された社会経済的組織・制度による外面的強制が必要不可欠である。
このように、法と制度はいわば表裏一体の関係にある。しかし、法がその要請に応えるためには、要請を担保するための組織・制度が存在しているだけでは十分ではない。そこには、そうした組織・制度を動かす人が必要である。
以上を鑑みるに、法システムは法文化・制度および法実践主体の一種の関数関係の中において歴史的に生成し、発展していくものである。
このように考えるならば、法の定義が論者によって多様であるということは、各論者が法に関する関数関係(法システム)をどのように捉えているとということに帰着する。
3、法の存立を決定付けるものとして、規範を挙げることができる(ヴィノグラドフ『法における常識』)。
特に、法は社会規範の一つであるということができる。
しかし、社会規範は法だけではない。すなわち、法は社会規範の下位概念である。社会規範の中には法以外にも道徳・習俗など様々なものがある。そして、法と道徳・習俗などそのほかの社会規範に含まれる諸要素とを区別する本質的要素として、①平均的人間の社会規範、②社会全体の社会規範、③人倫における客観的道理の社会規範、④強制を本質とする社会規範、⑤正当性の確信に裏付けされた社会規範という5つの要素を挙げることができる。
(1)①について
法システムにおいて想定されるのは、有徳の聖人君子ではなく、平均的人間としてのhomo juridicusである。
法はこの意味において、道徳とは異なる。法の制定・運用において、homo juridicusが平均的人間であるということを見誤ると法はシステムとして機能しなくなる(1919年米国「禁酒法」の例)。
(2)②から⑤について
ホランド(Thomas Erskine Holland)は、法と国家権力による強制との結合を法の本質的要素としている(国家説)。
しかし、この説は国家至上の一元的国家論の特殊近代国家の国家概念を普遍化するという過誤を犯していると言わざるを得ない。
これに対して、国家であると否とを問わず、ある一定の目的・利益を追求するために意識的に組織された各種の社会経済的団体にはそれぞれの部分社会に固有の法があるとする考えもある(部分社会説)。
確かに、この説は国家と各種の社会経済的団体との区別をなくすという点において、一元的国家論の欠点を克服している。
ところが、この説を徹底させると、反道徳的な社会経済団体においても固有の法の存在を認めることになるという不都合を生じることになる。
そもそも、「道徳-善が究極的には各人の人格の理想化に結びつくのに対して、法-正義は社会秩序の理想化に結びつく」(団藤)といわれるが、「法をピラミッド型にたとえるならば、その底辺において道徳と接着」(団藤)しているといえる。従って、人倫の道理に反する規範を法として認めることは出来ない(③)。
また、部分社会の内部的規範はそれぞれが個別にかつ独立して存在していると考えるべきではなく、社会経済システムの中における統一的一体性(システム性)としての法システムの中にこそ存在しているというべきである。
このように考えるならば、部分社会論は法の存立基盤を拡大しすぎているといえよう。 国家説および部分社会説の欠点を克服しようとするのが、法は全体社会を基盤として存立し(②)、典型的には、全体社会における組織的強制(④)を効力保持手段として持つものであるという考えである(全体社会説)。
法と道徳は、 拘束力を持つ(binding)、すなわちある行為を義務づけるという点で、マナーなどの他の規則からは区別される。そして、法は、公権力による強制を伴うという点で道徳から区別される。
しかし、法を自発的に遵守しようという人々の意識なくして、強制だけによっては、法を遵守させることはできない(ヴィノグラドフ Vinogradoff)。
「法の存立について決定的な意味を持つものは、物理的強制が加えられる可能性があるということよりも、むしろ、社会的権力によって課せられた規範を承認するという精神的な習慣(mental habit)であるということを意味している」(ヴィノグラドフ『法における常識』)と言われる。
すなわち、公権力による強制力は法の本質的な特徴といえる。とはいえ、公権力による強制は法にとって本質的な属性ではなく、法の存立には人々の正当性の確信がなければならない(⑤)。
この正当性の確信はまた社会規範のひとつである習俗と法とを区別する(いわゆる「民衆の法的確信」,Friedrich Carl von Savigny)。
|